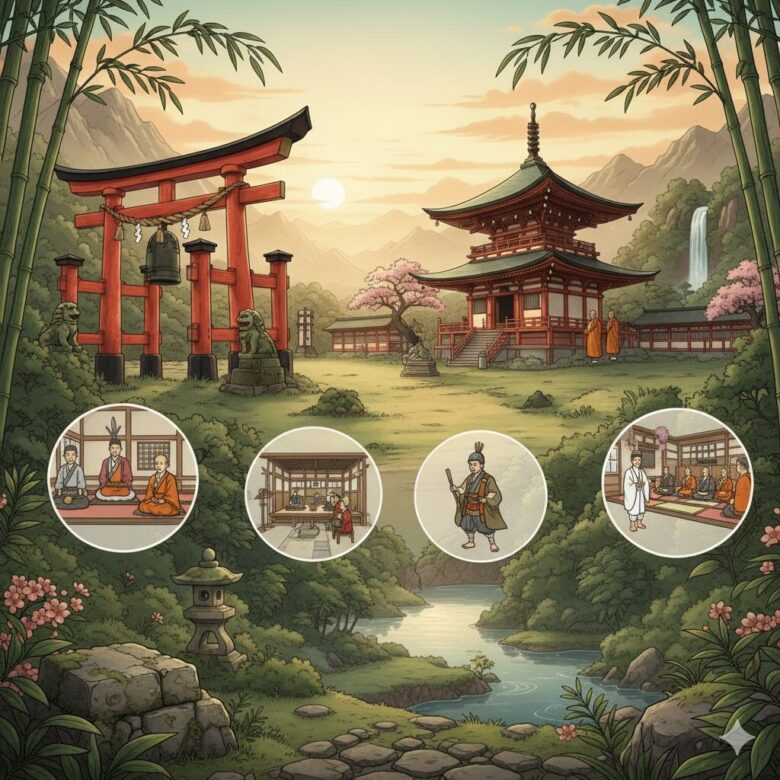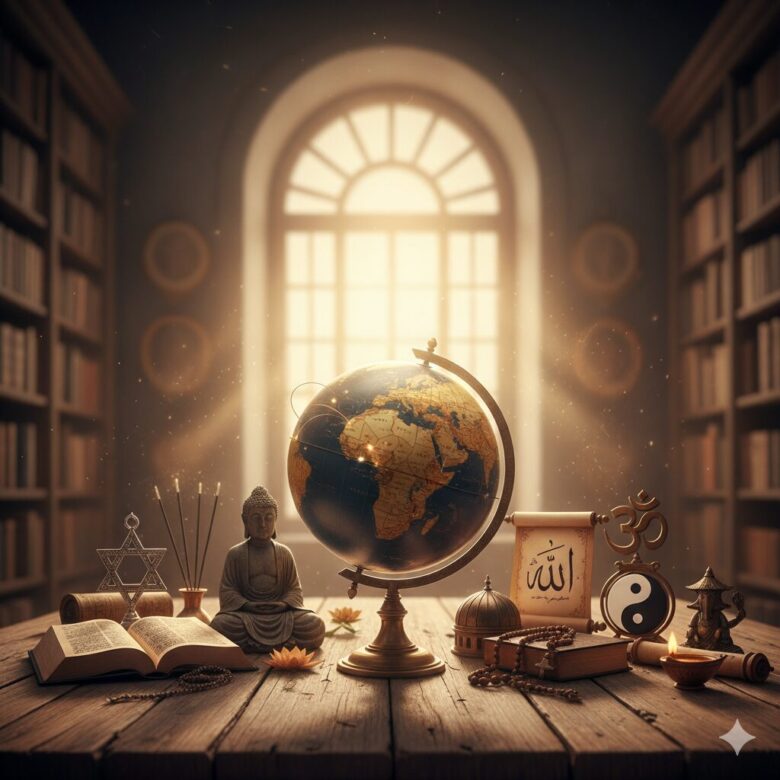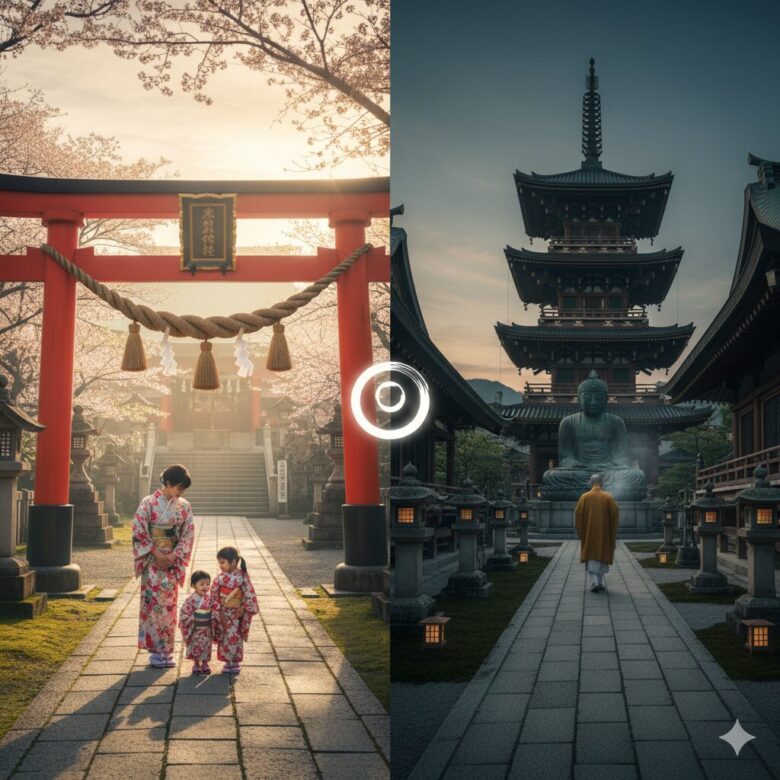「あなたの宗教は何ですか?」
こう聞かれたら、 多くの日本人は「無宗教です」と答えるでしょう。
しかし、 年末年始には「初詣」に行き、 神社でおみくじを引き、 受験や安産を「神頼み」する。
「無宗教ありえない」 海外の人から見ると、 この行動はとても不思議に映るそうです。
自分でも矛盾しているかも、 そう感じたことはありませんか?
この記事では、 なぜ日本人が「無宗教」と答えながらも、 神様や仏様に手を合わせるのか、 その「見えない信仰心」の正体に迫ります。
実は、 日本人の「無宗教」は、 「信仰心がない」という意味ではなかったのです。
▼この記事でわかること
- 日本人が「無宗教」と答える本当の理由
- データで見る日本人のリアルな宗教観
- 生活に溶け込む「見えない信仰心」の具体例
- なぜ海外では「無宗教=ありえない」と捉えられるか
目次
「無宗教」が多数派?データで見る日本人の宗教観

「自分は無宗教だ」 そう感じている人は、 どのくらいいるのでしょう。
まずは客観的なデータから、 日本人の宗教観を見ていきます。
統計で見る「自分は無宗教」と考える人の割合
2018年にNHKが行った、 「日本人と宗教」に関する意識調査があります。
それによると、 「信仰している宗教はない」と答えた人は、 全体の62%にのぼりました。
「信仰している宗教がある」と答えた人は36%です。 年代別で見ると、 若い世代ほど「宗教はない」と答える割合が高くなります。
この数字だけを見れば、 日本は「無宗教」が多数派の国だと言えそうです。
一方で「初詣」に行く人は約9,939万人
では、 本当に行動も「無宗教」なのでしょうか。
警察庁の発表(2015年)によると、 正月三が日の初詣の人出は、 全国で約9,939万人でした。 ※現在は警察庁による統計発表は終了しています。
日本の総人口が約1億2千万人ですから、 驚異的な数字です。
「信仰する宗教はない」と答えた62%の人々。 その多くが、 初詣に参加している計算になります。
ここに大きな「ズレ」があると思いませんか。
「宗教」と「信仰」の言葉の壁
この「ズレ」こそが、 日本人の宗教観の核心です。
多くの日本人は、 「宗教」と「信仰」を、 無意識に分けて捉えています。
- 宗教 = 特定の教団、教祖、厳格なルール(入信など)
- 信仰 = 神様や仏様、ご先祖様を敬う気持ち、習慣
「無宗教です」という答えは、 「特定の教団には属していません」 という意味合いが強いのです。
「神様なんて信じない」 という意味ではないことが分かります。
なぜ日本人は「無宗教」と答えるのか

では、 なぜ日本人は「宗教」という言葉に、 特定のイメージを持つようになったのでしょう。
その背景には、 いくつかの理由が考えられます。
「宗教」という言葉への抵抗感
皆さんにとって「宗教」とは、 どんなイメージでしょうか。
「厳格な戒律」 「熱心な勧誘」 「お布施や献金」
こうしたイメージが、 少しネガティブなものとして、 先に立ってしまうことがあります。
そのため、 「自分はそこまで熱心ではない」 という謙遜(けんそん)や、 少し距離を置きたいという心理から、 「無宗教」と答える方が楽だと感じる傾向があります。
特定の教団に属していないという意識
キリスト教やイスラム教のように、 「神との契約」や「入信の儀式」が、 日本古来の神道や仏教には、 あまり明確ではありません。
生まれた時から家に仏壇があり、 地域の神社の氏子(うじこ)である。
それが当たり前すぎて、 「自分がどの宗教に属しているか」 意識する機会が少ないのです。
「あなたは〇〇宗です」 と明確に言える人が少ないため、 結果として「特にない=無宗教」と答えてしまいます。
過去の事件などが与えた影響
残念ながら、 日本では過去に宗教団体による、 深刻な事件(オウム真理教事件など)がありました。
そうした報道の影響で、 「宗教=怖いもの、怪しいもの」 というイメージが、 強く刷り込まれてしまった面も否定できません。
「宗教」について語ること自体が、 少しタブー視されるような空気も、 「無宗教」と答える心理を後押ししています。
生活に息づく「見えない信仰心」の正体

「特定の宗教はない」 そう答える日本人ですが、 私たちの生活は「見えない信仰心」で溢れています。
それは非常に穏やかで、 文化や習慣と一体化したものです。
「八百万(やおよろず)の神」という感覚
日本には古来、 「八百万の神」という考え方があります。
山、川、海、岩、木、 さらには台所やお米一粒にまで、 神様が宿るとされてきました。
これは「アニミズム(自然崇拝)」と呼ばれます。
だからこそ日本人は、 自然災害に「神様の怒り」を感じたり、 モノを粗末にすることに、 「バチが当たる」という罪悪感を抱いたりします。
これは特定の教義ではなく、 日本人の心に深く根付いた、 「見えない信仰心」そのものです。
ご先祖様を大切にする「お盆」や「法事」
お盆に故郷へ帰り、 お墓参りをする。
命日には法事を行い、 ご先祖様を供養する。
これは仏教の行事ですが、 多くの日本人が宗教的な意識なしに、 「大切な習慣」として行っています。
「ご先祖様が見守ってくれている」 そう感じる心は、 立派な信仰心の一つと言えるでしょう。
「いただきます」に込められた感謝
食事の前に言う「いただきます」。 これは、 食材となった動植物の「命」と、 それを作ってくれた人への「感謝」の言葉です。
ここにも、 すべてのものに命や魂が宿る、 という日本の精神性が表れています。
他にも、
- 七五三に子供の成長を感謝する
- 神社で「良縁」や「合格」を祈願する
- 事故に遭った時「神様のおかげで助かった」と思う
これらすべてが、 日本人の「見えない信仰心」の表れです。
海外から見たら「ありえない」?一神教との決定的な違い

この日本人の感覚が、 海外、 特に一神教(キリスト教、イスラム教など)の国々から見ると、 非常に理解しがたいものです。
世界における「無宗教(無神論)」の立場
多くの国において、 「I am an atheist.(私は無神論者です)」 と宣言することは、
「神の存在を明確に否定します」 という意味を持つ、 非常に強い態度の表明です。
そのため、 日本人が安易に「無宗教(No religion)」と答えると、 「神を一切信じない人」 「道徳心のない人」 と誤解されてしまうことすらあります。
海外で「無宗教」と答えることは、 「ありえない」と驚かれる、 非常にデリケートな問題なのです。
クリスマスも祝う日本人の柔軟性
日本人は、 神社に初詣に行ったかと思えば、 クリスマスにはツリーを飾って祝います。
お葬式は仏教式なのに、 結婚式はキリスト教式(チャペル) ということも珍しくありません。
これは、 八百万の神々を受け入れてきた、 多神教の国ならではの「柔軟性」です。
「良いものは何でも受け入れる」 この大らかさが、 日本文化の特質とも言えます。
しかし一神教の観点からは、 「自分の信じる神は唯一絶対」であるため、 他の神様を同時に拝むことは、 ありえない行為なのです。
私の体験談:海外で「宗教は?」と聞かれて困った話
私(筆者)も学生時代、 オーストラリアに短期留学した際、 ホストファミリーから、 「シュン(仮名)の宗教は?」 と笑顔で聞かれた経験があります。
私は例にもれず、 「アイム・ノー・レリジョン(無宗教です)」 と答えました。
すると、 彼らの顔が少し曇ったのを覚えています。
「でも、 お正月には神社に行くし、 困った時は神様にお祈りするよ」
そう慌てて付け加えると、 彼らはキョトンとして、 「それは仏教なの? 神道なの?」 とさらに質問されました。
当時の私はうまく説明できず、 「日本人はみんなそうなんだ」 としか言えませんでした。
あの時の「不思議なものを見る目」は、 今でも忘れられません。 日本人の宗教観を説明するのが、 いかに難しいかを痛感した体験です。
日本人の「無宗教」は信仰がないという意味ではない

日本人が口にする「無宗教」。 それは決して、 神仏やご先祖様を敬う心がない、 という意味ではありません。
特定の教団に属していないだけで、 私たちの生活には、 自然への感謝や、 目に見えない存在への畏敬(いけい)の念、 いわば「見えない信仰心」が、 文化や習慣として深く溶け込んでいます。
「無宗教ありえない」 という視点は、 宗教への向き合い方が世界には多様にある、 ということを教えてくれます。
もし次に、 「あなたの宗教は?」と聞かれたら、
「特定の宗教はありませんが、 私たちは自然やご先祖様に感謝する心を大切にしています」
そう答えてみるのは、 いかがでしょうか。 きっとそれが、 日本人の素直な感覚に一番近い答えだと思います。